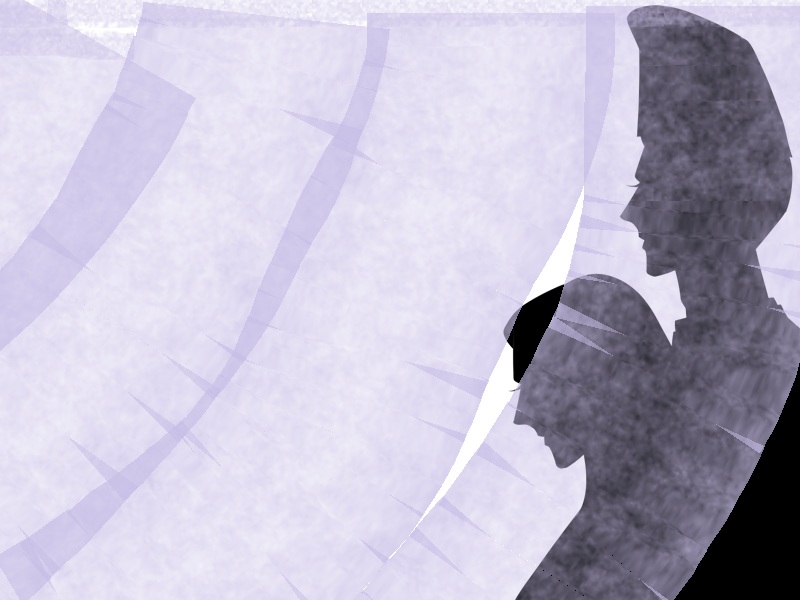3. あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の 長々し夜を ひとりかも寝む / 柿本人麿
(読み)あしびきの やまどりのおの しだりおの ながながしよを ひとりかもねん / かきのもとのひとまろ
(訳)山鳥の長く垂れ下がった尾のようにこの長い夜を私は1人寂しく寝るのでしょうか。
(語句)
・「あしびきの」は「山」にかかる枕詞。
・「の」を繰り返すことで長い夜を表現している。
・ひとりかも寝む・・ひとりで寝るのだろうか
「寝(ね)(未然)」+「む(推量)」
※「寝(ぬ)」はナ行下二段(ね・ね・ぬ・ぬる・ぬれ・ねよ)
(解説)
・元々は万葉集の詠み人知らずの歌とされる。
(作者)柿本人麿:万葉集の歌人。(万葉集では「柿本人麻呂」、平安時代は「人麿」「人丸」などと表記される。)
天皇をたたえる歌、相聞歌(そうもんか/恋の歌)、挽歌(ばんか/死を悼む歌)などすぐれた歌を多数残す。
「歌聖(かせい/うたのひじり)」と仰がれる。三十六歌仙の一人。
持統天皇、文武天皇(軽皇子)に仕えた宮廷歌人。岩見国(島根)で亡くなったとされる。
・亡き妻を思い詠んだ歌
笹の葉は み山もさやに さやげども 我は妹(いも)思ふ 別れ来ぬれば(万葉集)
(訳)笹の葉は、この山にさやさやと(心乱せというように)風に吹かれて音を立てているけれど、私は妻のことを一筋に思っています。別れてきてしまったので。