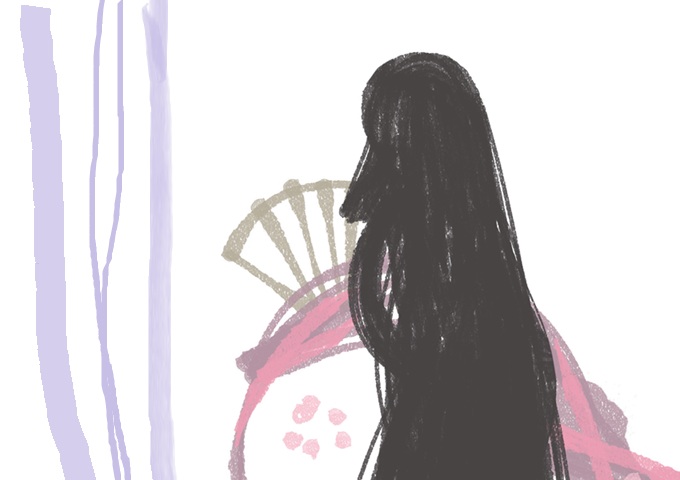2. 春すぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山 / 持統天皇
(読み)はるすぎて なつきにけらし しろたえの ころもほすちょう あまのかぐやま / じとうてんのう
(訳)春が過ぎていつのまにか夏が来たらしい。天の香具山に真っ白な衣が干してあるのだから。
(語句)
・「けらし」・・「ける」+「らし」(推定)
※「らし」は客観的な事実に基づいた推定。「①客観的な事実」があって+「②だから~らしい」と推定する。この歌は倒置法で「②~らしい」+「①だって~(事実)だから」となる。
・「白妙の」・・「衣」にかかる枕詞。白い布。「白妙の」は他に雪、雲、袖、ひもなどにかかる。
・「てふ(ちょう)」・・「といふ」が詰まったもの
(解説)
・さわやかな夏の情景と伝説の山の神秘性を感じる歌。
・「万葉集」では「春過ぎて 夏来たるらし 白妙の 衣干したり 天の香久山」となっている。
万葉集の方は「干したり」で目の前のことを歌っているが、「新古今集」の「干すてふ(干すといふ)」では、「干すと伝えられている」と、天の香具山の伝承を取り込むような形になっている。
・天上から降りてきたという神話的な伝説から「天の」を冠する。
(作者)持統天皇:40代目天皇。天智天皇(1「秋の田の」)の第二皇女(おうじょ・ひめみこ・こうじょ)。天武天皇の妻。都を飛鳥から藤原の地へ移す。日本最古の都、藤原京を開いた。
天の香具山は、神の住む山とされている。現在の奈良県橿原市。
「大和三山」は「香具山(かぐやま)」、「畝傍山(うねびやま)」、「耳成山(みみなしやま)」。信仰の対象とされていた。

藤原宮から見て左手に「天の香具山」が見えたと思われる。後ろに耳成山、右手に畝傍山。