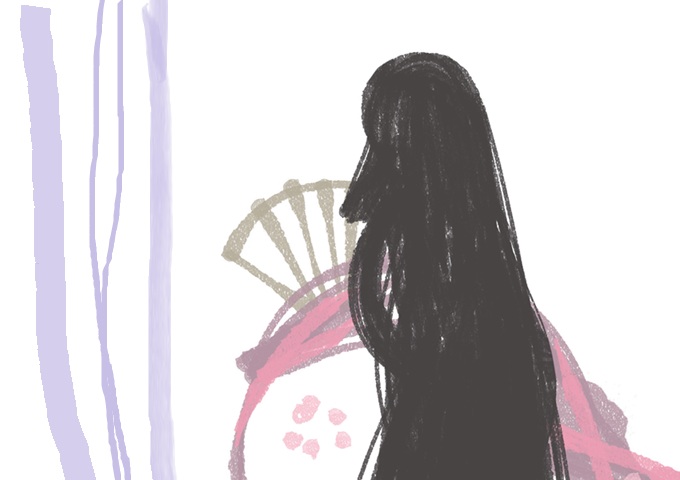51. かくとだに えやはいぶきの さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを / 藤原実方朝臣(ふじわらのさねかたあそん)
(読み)かくとだに えやはいぶきの さしもぐさ さしもしらじな もゆるおもいを
(訳)このように伝えることさえできないのですから、伊吹山のさしも草のようにそれほどのものとは知らないでしょうね。燃えるこの想いを。
(解説)
・さしも草・・ヨモギ。お灸に使われた。
・えやはいう・・言うことができようか。いやできない。
(作者)藤原実方朝臣。(ふじわらのさねかたあそん)。貞信公(藤原忠平)(26「小倉山」)のひ孫。66代一条天皇に仕えた。
光源氏のモデルの1人と言われている平安後期の色好み。(平安前期は在原業平。)
清少納言と恋仲?藤原行成と口論になり冠を叩きつけたため陸奥守に左遷。