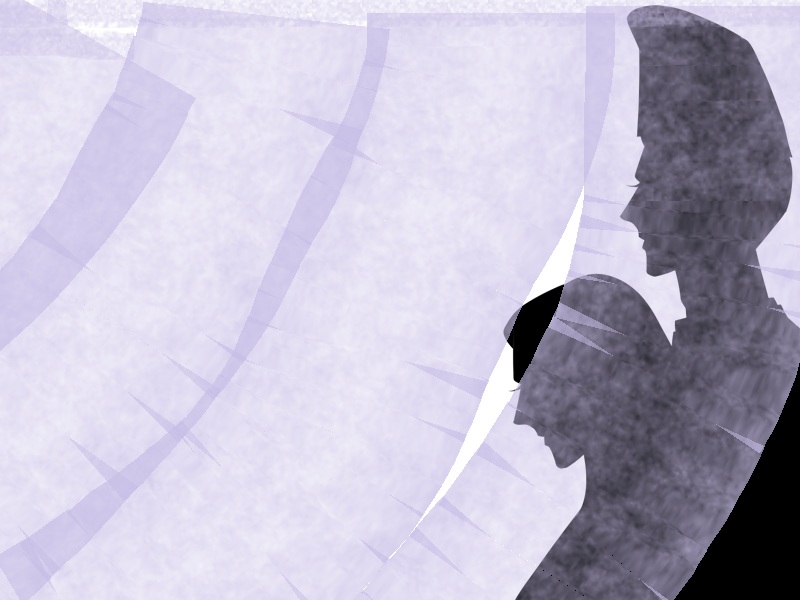(ヒトリシズカ)
41. 恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか / 壬生忠見(みぶのただみ)
(読み)こいすちょう わがなはまだき たちにけり ひとしれずこそ おもいそめしか
(訳)恋をしている私のうわさは早くも広まってしまいました。誰にも知られないように心の中で思い始めたばかりなのに。
(解説)
・まだき・・早くも
・960年・天徳内裏歌合わせで40「しのぶれど」と対決した。摂津からはるばる都にやってきた。
(作者)壬生忠見(みぶのただみ)。摂津国の下級役人。父は壬生忠岑(30「有明の」)。
父子ともに三十六歌仙。